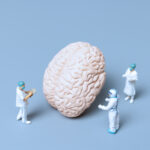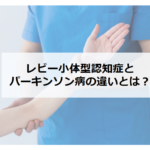認知症の症状といえば、どのようなものを思い浮かべますか。ほとんどの方が、「物覚えが悪くなる」「物忘れが激しくなる」などの、記憶に関する障害を想像するでしょう。
しかし、認知症には複数の種類があり、記憶障害以外にもさまざまな症状が現れます。
記憶障害とは違った症状が強く出ることもあり、時には医師が誤診をしてしまう場合もあると報告されています。
今回は複数ある認知症の中でも、記憶障害以外の症状が多く現れると言われている「レビー小体型認知症」について徹底解説します。
また、 認知機能検査を実施しているお近くの医療機関は、こちらからお探しください。
レビー小体型認知症(れびーしょうたいがたにんちしょう)とは
レビー小体型認知症とは、「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」と肩を並べる、代表的な「3大認知症」の1つです。
その中でも、「アルツハイマー型認知症」に次いで2番目に多い認知症です。
2019年の厚生労働省の発表によると、レビー小体型認知症の患者数は、日本の認知症患者の約4〜5%の割合を占めるとされています。
しかし、誤診や見落としによりレビー小体型認知症と診断されていない方を含めれば、10〜30%にも上るとも言われており、未だ解明されていない点も多い病状です。
記憶障害を中心とした認知機能低下の他に、身体が上手く動かせなくなるパーキンソン症状、非常にリアルな幻視や睡眠障害などの症状があらわれるため、レビー小体型認知症の診断は非常に困難と言われています。
また、レビー小体型認知症の初期症状には精神疾患がみられることもあるため、うつ病や統合失調症であると間違えて診断されることもあります。
70歳から80歳の高齢者に多く見られますが、稀に65歳未満で発病する場合もあると言われており、アルツハイマー型認知症と違い、遺伝による発病のケースは少ないと考えられています。
出典:「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」(厚生労働省老健局)
レビー小体型認知症の原因
レビー小体型認知症の原因は、「レビー小体」というタンパク質が脳内に蓄積されることと考えられています。
合理的で分析的な思考や言語を司る「大脳皮質」や、呼吸や心拍、運動機能と密接に関わる「脳幹」に集まることでレビー小体型認知症を発症します。
特に「脳幹」の神経細胞が破壊されると、身体を自由に動かすことが困難になる「パーキンソン症状」に繋がります。
また、レビー小体は、脳に限らず全身の神経細胞にできます。
脳以外の神経細胞がレビー小体によって破壊されると、「頭痛」や「立ち眩み」、「便秘」や「嗅覚障害」を引き起こします。
レビー小体が脳に現れる明確な理由は分かっていませんが、現段階では、脳の年齢的な変化が原因だと考えられています。
レビー小体型認知症の症状

レビー小体型認知症の症状は、一般的な認知機能の低下に留まりません。医師ですら、レビー小体型認知症を誤診してしまうケースも過去に報告されています。
どのような症状が現れるかを事前に把握し、早期発見に努めましょう。
3つの中核症状
パーキンソン症状
パーキンソン症状とは、身体の筋肉が硬直を始め、意図せずに手足の震えが起こったり、動きが遅くなる、筋肉が硬直するなどの症状がでたりする事を言います。
「パーキンソン病」という、長い時間をかけて徐々に運動機能が衰えていく病気と症状が酷似しています。
運動性のパーキンソン症状は主に無動・寡動(むどう・かどう)、静止時振戦(せいしじしんせん)、筋強剛(きんきょうごう)、姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい)の4つに分けることができます。
無動・寡動(むどう・かどう)
・歩く速度が遅い
・無表情
・書く文字が小さくなる
静止時振戦(せいしじしんせん)
・止まっていると手足が震える
・動き出すと震えがおさまる
筋強剛(きんきょうごう)
・顔がこわばる
・肩や手指の筋肉が固くなる
姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい)
・転びやすくなる
・バランスがとりづらい
身体を動かすことが困難になっていくため、転倒などによるケガには十分な注意が必要です。
進行すれば身体全体を動かせないようになってしまったり、嚥下障害を来たしたりして、日常生活が送れなくなってしまう場合もあります。
幻視
他人には見えない、存在しないものが見える症状が幻視です。レビー小体型認知症を発症した方の多くが幻視を見ます。
「部屋に動物がいる」「じっとこちらを見ている人がいる」などの、非常にリアルな幻視を見るという特徴があります。
人によっては幻視を見ていると理解している人もいますが、幻視だと理解できずに、他人から見ればおかしな行動をとってしまう人もいます。
認知機能の変動
レビー小体型認知症の症状の1つに、患者の認知機能がその日の調子によって変わることが挙げられます。日によって状態が変化する場合もあれば、一日の中でも激しく変化する場合も報告されています。
時間や場所、天気など様々な要因が絡んでいると考えられていますが、未だはっきりとしたことは解明されていないのが現状です。
その他の症状
レム睡眠行動障害
一般的に睡眠は、脳を休息させ、脳や肉体の疲労回復をさせる「ノンレム睡眠」と、脳が活発に動き、記憶を整理する「レム睡眠」が交互に現れると考えられています。
通常、レム睡眠の場合は脳が活発に動き夢を見ますが、身体は休息状態になり弛緩(しかん)します。
しかし、レム睡眠行動障を発症した場合、レム睡眠の状態であっても身体が弛緩しません。「大声を出す」「暴れる」などの、夢の中での行動がそのまま寝言や寝相として現れます。
レム睡眠行動異常はレビー小体型認知症の前兆、もしくは初期段階に多く報告されています。寝言や寝相が激しい方は、レビー小体型認知症の始まりの可能性があります。
自律神経症状
レビー小体型認知症の方は、自立神経の働きが悪くなり、血圧のコントロールが上手くいかなくなることがあります。
急に立ち上がった時などに立ち眩みが起こったり、時には失神してしまう方もいます。
また、頻尿、便秘、多汗、唾液が飲み込めないなどの、自律神経に関わる症状が発症するケースも報告されています。
薬に対する過敏反応
レビー小体型認知症には薬剤過敏性という特徴があり、服用する薬物の量が指定の用量以下でも過敏に反応して副作用が強く出たり、興奮作用を起こしたりすることが報告されています。
特に抗うつ薬や抗不安薬、睡眠導入剤などの向精神薬に対しての過敏性が見られるようです。
場合によっては薬によって症状が悪化してしまうこともあり、レビー小体型認知症の方が薬を服用する際は注意が必要です。
薬を服用する場合はごく少量から始め、薬の効果や認知症の方の反応を見つつ、用量を増やしたり薬の種類を変えたりする必要があります。
抑うつ症状
レビー小体型認知症の症状の1つに、抑うつ症状があります。
特に初期段階で現れやすく、「気分がふさぎこむ」「憂鬱になる」「無気力、悲観的になる」といった症状が現れます。
また、身体的な症状として「不眠」「身体のだるさ」「食欲不振」などが現れる場合もあると言われています。
そのほかの認知症の症状と比較してみたい方は、こちらの記事から「アルツハイマー型認知症」と「脳血管性認知症」と比較してみると良いでしょう。
脳血管性認知症とは?症状や原因、「まだら認知症」との関係を徹底解説
アルツハイマー型認知症とは?初期症状や平均寿命、治療法を解説!
レビー小体型認知症の平均余命と突然死

レビー小体型認知症は長生きするのか?レビー小体型認知症の方の平均余命は7年から10年と考えられており、アルツハイマー型認知症よりも短いと言われています。
パーキンソン症状が徐々に進み、認知機能も衰えていくことから、末期には寝たきりの状態になり一日中介護が必要な状態になる場合がほとんどです。
また、レビー小体型認知症のパーキンソン症状によって、体中の筋肉の動作が衰え転倒したり、嚥下障害による食事中の窒息などの突然死が報告されています。
レビー小体型認知症の方を介護する場合は、転倒や嚥下障害などによる突然死のリスクを避ける努力をしなければなりません。
床にコード類を置かない、リンゴのすり身などの飲み込みやすいものを食べさせるなどといった工夫が必要です。
レビー小体型認知症診断基準と診断方法
診断基準
レビー小体型認知症の診断基準は、「一般社団法人日本神経学会」によって以下のように記されています。
患者の症状の中に、認知機能の低下に加えて、「中核的特徴」と呼ばれる以下の3つの内2つ以上が当てはまれば、「ほぼ確実にレビー小体型認知症である」と診断されます。
1. 認知機能の変動
2. くり返し具体的でリアリティのある幻視
3. パーキンソン症状
また、上記の3つの「中核的特徴」のうちの1つ以上に加え、下記の「示唆的特徴」のうち1つ以上が当てはまる場合も「ほぼ確実にレビー小体型認知症」と診断されます。
1. レム睡眠行動異常症
2. 抗精神病薬に対する重篤な過敏性
「中核的特徴」が1つのみ、もしくは「示唆的特徴」が1つのみ当てはまる場合は「レビー小体型認知症の疑いあり」という診断が下されるのが一般的です。

出典:認知症診療ガイドライン2017_700_第7章(一般社団法人日本神経学会)を基に自社で作成
診断方法
認知機能に関する問診
認知機能の検査の1つに、医師による問診があります。
①HDS-R(長谷川式簡易知能評価スケール)
②MMSE(ミニメンタルステート検査)
の2つが代表的に用いられることが多い初期の1次スクリーニング検査となります。
いずれも医師と患者の問答形式であり、患者の年齢や当日の日時確認、簡単な計算などを医師が口頭で質問します。
これらに患者が答えていくことで認知機能を測るテストです。
HDS-RもMMSEも、レビー小体型認知症のみではなく、アルツハイマー型認知症などその他の認知症の検査にも多く使われています。
レビー小体型認知症に関する問診
幻視やパーキンソン症状の自覚があるか、心が沈む時やめまい、立ち眩みがあるかなどの、レビー小体型認知症に該当する症状の自覚があるかを問診します。
上記のHDS-RやMMSEの問診は、認知機能の低下が起こっていないレビー小体型認知症の方には効果が期待できないというデメリットがあります。
一方こちらの問診は、認知機能の低下以外の初期症状を患者から直接症状を聞き出すことができるため、比較的発見に繋がりやすいと考えられています。
画像検査
MRIやCTスキャンなどから脳の画像を取得し、異常が無いかを検査する方法です。
脳の萎縮やパーキンソン症状の有無、脳血流に異常が起きていないかを調べる事ができます。
レビー小体型認知症の他にも、別の原因で脳に異常を来していないかを調べることができます。
誤診されやすい症状

レビー小体型認知症は診断が遅れてしまうことや、他の病気と誤診してしまうことがあると報告されています。
その原因の1つに、認知機能の低下以外にも多くの症状が付随していることが挙げられます。
パーキンソン病
パーキンソン症状は、レビー小体型認知症の初期から発症する特徴的な症状です。
認知機能の低下が確認されるよりも先に症状が出始める場合が多いため、レビー小体型認知症と診断される前にパーキンソン病と診断されてしまう場合があります。
パーキンソン病もレビー小体型認知症と同様に、脳内にレビー小体が確認され、進行によって認知機能の低下が見られる為、見分けをつけることが困難とされています。
現段階では、パーキンソン病の症状から始まったケースでは、1 年以内に認知症の症状が出てきた場合はレビー小体型認知症と診断し、それ以降に認知機能症状が出てきた場合は認知症を伴うパーキンソン病と診断されているようです。
うつ病
レビー小体型認知症の初期に見られる抑うつ反応が、うつ病と診断される場合が報告されています。
認知症を専門としていない医師がレビー小体型認知症の抑うつ症状を持った方を診断する場合に起こり得ると考えられます。
レビー小体型認知症の特徴の1つに薬剤過敏性があり、医師の指示のもと処方された抗うつ剤などの薬に過敏に反応してしまい、症状を悪化させるというケースも報告されています。
統合失調症
レビー小体型認知症の幻視が、統合失調症に由来する幻視と誤診されるケースが報告されています。
レビー小体型認知症の幻視は、認知機能の低下が確認されなくとも発症することがあります。患者の意識がはっきりしている状態で見る幻視は、認知症と診断され難いのではと考えられます。
統合失調症の誤診の場合も、うつ病の誤診の場合と同様に、医師の指示の診断のもと処方された薬に患者が過敏に反応し、症状を悪化させるケースが報告されています。
レビー小体型認知症の治療方法
レビー小体型認知症を治療する方法は、現段階では見つかっていません。
現在では、パーキンソン症状などの、出た症状に対する薬を処方していくことが主な治療法となっております。
しかし、レビー小体型認知症の方は薬に過敏に反応する性質があることに注意が必要です。
抑うつ症状や幻視などの症状の改善を目的に処方される向精神薬は、特に過敏性の反応が見られると報告されています。
最初は少しの用量だけ処方し、様子を見ながら用量を増やすことで、その人に適した量を見極める必要があります。
認知症は早期発見と定期的なセルフチェックが重要
認知症は、早期に発見して適切な治療を施すことで、その進行を遅らせられる病気です。
そして、早期発見には定期的に認知機能をチェックすることが重要になります。
MCI段階で発見すれば進行を抑制できる
認知症の一歩前の段階にMCI(軽度認知障害)という状態があります。
物忘れなど認知症に見られる症状が出ているものの、その程度は軽く周囲に影響を及ぼすほどではない状態です。
しかし、軽度とはいえMCIを放置すると、その中の約1割の方は1年以内に認知症を発症すると言われています。一方で、もしMCI段階で適切な治療を施すことができれば、健常な認知機能まで回復する可能性が14〜44%もあるとされています。
つまり、認知症を深刻化させないためには、少しの認知機能の変化に気づき、適切に対応することが有用であると考えられます。
🔰認知機能検査を実施しているお近くの医療機関は、こちらからお探しください。
レビー小体型認知症に関しては、以下の記事もご覧ください。
レビー小体型認知症になると寝てばかりになる?よく寝る理由や原因について解説